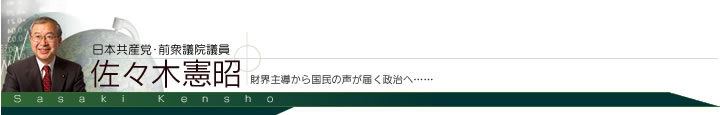奮戦記
【03.06.04】財金委で生保・年金カット法案について質問しました
 今日は、財務金融委員会で保険業法改正案について質疑がおこなわれました。
今日は、財務金融委員会で保険業法改正案について質疑がおこなわれました。
午前中は、参考人にたいする質疑、午後には竹中金融担当大臣にたいする質疑がおこなわれました。
私は、まず国民の支持が得られていない問題を指摘しました。
金融審議会金融分科会第二部会が、小泉内閣発足直後の平成13年(2001年)6月26日に「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」を提出しています。
ここでは「契約条件の変更」についてこう書いています。
 ――「このような制度は、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めてその導入が可能となるものと認識している」。
――「このような制度は、その内容について国民・保険契約者の理解の上、社会的な認知が十分に得られてこそ初めてその導入が可能となるものと認識している」。
要するに、国民・契約者が理解し社会的な認知が得られていなければ、導入できないということです。
そこで私は、「社会的な認知が得られてた根拠を示せ」と言いましたが、竹中大臣はそれをまったく示すことができませんでした。
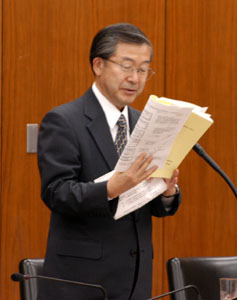 6月7日付の「週刊東洋経済」に、契約者にたいするアンケートの結果が紹介されています。――それによると、反対は52.6%と過半数に達しています。これにたいして、賛成はたったの5.8%にすぎません。(「判断できない」が41.6%)
6月7日付の「週刊東洋経済」に、契約者にたいするアンケートの結果が紹介されています。――それによると、反対は52.6%と過半数に達しています。これにたいして、賛成はたったの5.8%にすぎません。(「判断できない」が41.6%)
これをみても、いまでも社会的認知が得られていないことは明らかです。
金融審の「生命保険をめぐる総合的な検討に関する中間報告」では、「上述の意見募集結果を踏まえれば、現時点では、制度導入の前提となる環境が整っていないと判断せざるを得ず」と結論づけているのです。
この報告に、違反していることは明らかです。
「生保経営難」の原因と責任はどこにあるのか
 生保会社の経営難の原因はどこにあるのでしょうか。誰に責任があるのでしょうか。
生保会社の経営難の原因はどこにあるのでしょうか。誰に責任があるのでしょうか。
生命保険会社の本源的利益と言われる3つの損益、――費差損益、死差損益、利差損益についてみると、費差損益と死差損益については大きな利益が出ています。
業界全体としてみれば、3利源の合計ではプラスになっています。
たとえば、13年度(2001年度)について言えば、費差益は7898億円、死差益については2兆7067億円にのぼっている。この二つを見るとまったく問題はありません。
 ところが利差損益をみると、1兆5198億円の損失です。これは、明らかに低金利によって生まれたものです。
ところが利差損益をみると、1兆5198億円の損失です。これは、明らかに低金利によって生まれたものです。
しかしそれは、費差益と死差益によって埋め合わされ、結果として1兆9767億円、2兆円の利益が出ているのです。
そうなると、何が問題となるのか。株価の下落によって生まれた損失が問題になるのです。
金融庁の資料でも、「有価証券含み損益」は、2年前の7兆5696億円から今年3月の2兆9435億円へと約6割も下落しているのです。
 そうすると、いまの生保の経営難は、株の下落によって生み出されたものだということになります。
そうすると、いまの生保の経営難は、株の下落によって生み出されたものだということになります。
これらは、すべて政府の経済政策がもたらしたものではないでしょうか。
政府は、「不良債権処理」を強引にやってきました。倒産と失業が増える「デフレ要因だ」と認めながらやってきたのです。
しかも、今年から来年にかけて4兆円の国民負担増です。消費が低迷して経済の先行きがますます不透明になります。だから株価が落ちるのです。
こうなれば、経営が難しくなるのは当たり前です。追い込んだのは、政府ではありませんか。

.